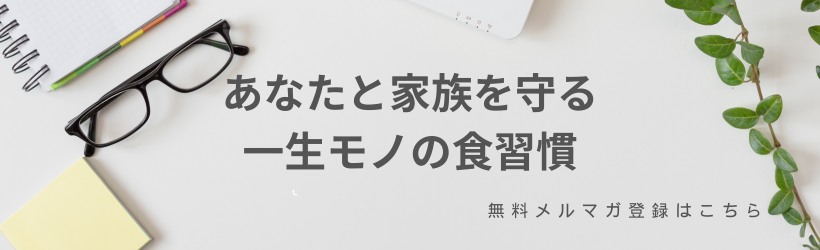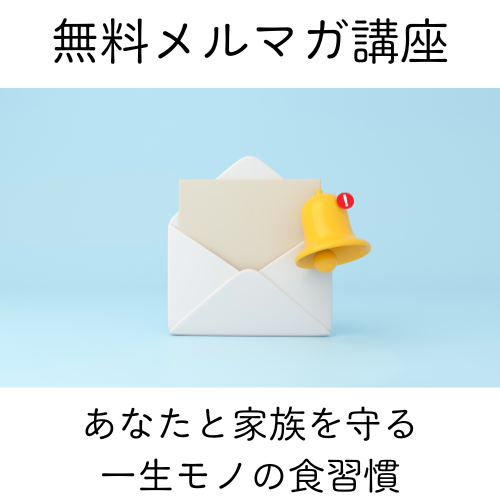わたしの原動力
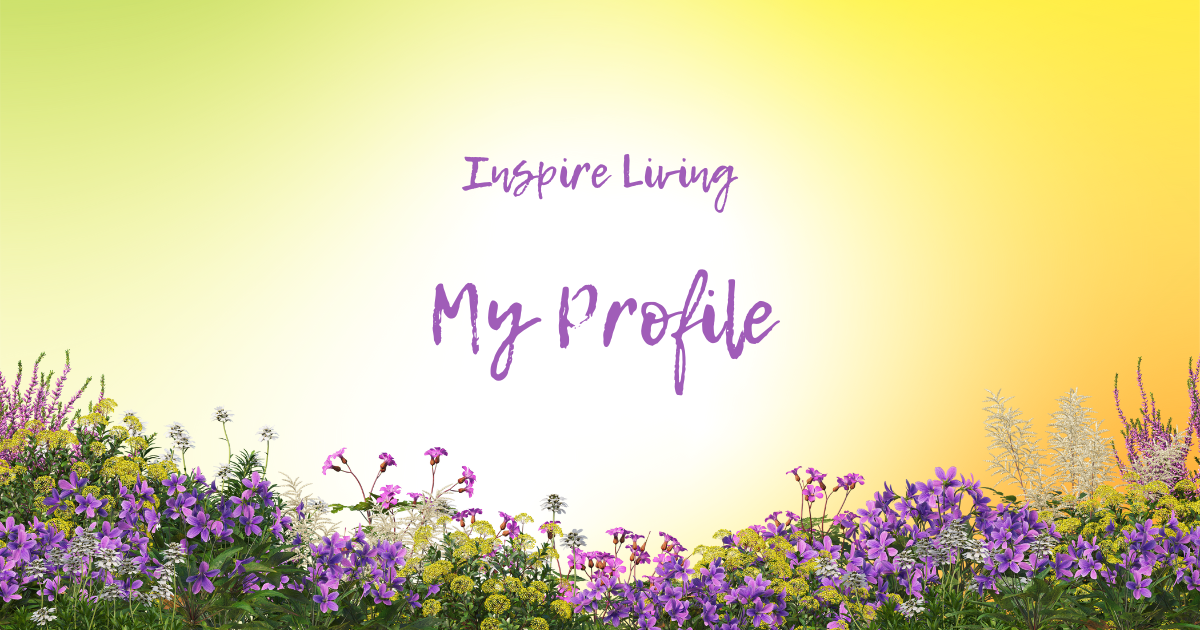
ここでは私のプロフィールをご紹介しています。
- 病院管理栄養士として働いてきた原動力や
- 介護離職した今、どのようなことに注力しているか
- 経歴や保有資格
について書いています。
・親の介護にあたっている方や、
・生活習慣病のある方にも参考になれば幸いです。
私はかつて、
最も身近な人を救うことができず、大きな後悔を抱えました。
そこから得た教訓を胸に、臨床現場で働いてきました。
ここでは、その原点となった祖父母のエピソードからお話させてください。

私の祖父母は、
大正生まれのオシドリ夫婦でした。
祖母は晩年
「長生きしすぎたわ」というのが口癖で、
その後 心の不調をきたしました。
祖父は、祖母をケアするため
終の棲家として整えてきた自宅を手放し、介護施設に夫婦同室で入所しました。
あるとき、
祖母は誤嚥性肺炎を発症し、入院しました。
抗生剤治療により肺炎は軽快しましたが、食事を摂れなくなってしまいました。
食べ物を飲み込むと、むせたり気道に入ってしまうのです。

高齢者の咀嚼・嚥下機能の低下はよくみられることで、
その対応は私の専門分野の一つです。
食事量の少ない状態が続く場合は、点滴から栄養を補給したりします。
ただしここで重要なことは、
「腕などの細い末梢血管からの栄養投与にはタイムリミットがある」
ということです。

ご存知でしたか??
「タイムリミット」というものがあるのです。
栄養管理をする側としては常識なのですが
一般の方にはあまり知られていないことかもしれません。
そして
そのタイムリミットは、2週間です。
2週間を目途に、
他の栄養投与法に切り替える必要があります。
なぜかというと、
細い血管からは、
- 十分な栄養を投与しにくいというデメリットや、
- 血管の炎症を防ぐ目的があるからです。

そのためそれ以降は、
栄養ルートを
- 太い血管に切り替えて栄養を入れるか、
- 胃や腸に小さな穴(胃瘻/腸瘻)をあけて栄養を注入するか、
- 場合によっては強制的な栄養投与を控え、自然の流れに任せるか・・・
いずれかの方法を選択する必要があります。
本人がしっかりしていればいいのですが、
そうでない場合は、
家族が意思決定する必要があります。

私はある日、
祖母の栄養投与法として、
「胃瘻を造設するのか、
またはナチュラルコースを選ぶのか、
医師から決断を求められている」ということを、家族から聞きました。
私が聞いたタイミングはおそらく、
点滴が開始されてから4週目に差し掛かる頃でした。
4週目
・・・
え、4週目??
・・・
タイムリミットである2週間を
だいぶ過ぎてしまっていたようなのです。
小柄で予備力のない91歳の祖母にとって、
末梢点滴で3週間以上過ごすというのは、
「じわじわと栄養を削ってジリ貧状態を作り出す」
のと同じようなものです。
ただし、
タイムリミットを過ぎそうな場合でもいくらかの対処法はあります。

細い末梢血管からの点滴であっても、
炎症が落ち着いていれば、
- 少し濃い組成に変更することはできますし、
- 点滴に適量の油分を加え、適切なスピードで投与することによって
栄養量を増やすこともできます。
この辺りは栄養管理をする側としては常識というか、
非常に重要なポイントです。
特に、家族の決断を待っている段階では、
「採血結果をみながら、食事量と点滴量のバランスをとるなどして、
ジリ貧状態にしない」
という調節が栄養管理に求められます。
患者さんの身体の状態を見ながら
このバランスをとっていく、というのが
NST(Nutrition Support Team)の仕事だったりします。
私が長年やってきた仕事です。

しかし悲しいことに
祖母の場合、
伝え聞いた話をつなぎ合わせる限り、
このあたりの調整が十分になされていなかったように思えます。
私の最大の後悔はここです。
たとえば、
こんなことを医師から問われたら、
あなたとあなたの家族はきちんと答えられるでしょうか?
Dr.
「栄養を入れる方法を決めないといけません。
ご家族でよく相談して、
水曜日までに回答をください。」
いきなり聞かれたら、
(え?? どういうこと??)と思うのではないでしょうか。
(栄養を入れる方法って何のこと?)
(どういうこと??)
と混乱します。
(しかも水曜日までにって・・・ずいぶん急じゃない??)
❓だらけの心境だと思います。

こういう時、
医療現場ではよくみかける光景なのですが、
家族の中で意見が割れることが多いのです。
我が家も同様でした。
祖母の今後の方針について、家族の中で意見が割れていました。
- ナチュラルコースを受け入れてもよいのではないかという意見や、
- そうは言っても諦めきれない祖父の心情に、
- もはやどうしたらよいのか分からないという嘆き。
家族が迷っている内に、回答期限はすぐに来てしまいます。
栄養投与の方法を切り替えるタイムリミットなんて、
すぐに来てしまうのです。
私の一番の後悔は、
自分の専門分野であるというのに、
祖母がどのように栄養管理されているのか、
情報収集を十分にしなかったところにあります。

当時私は妊娠していました。
働きながら、ひどいつわりに悩まされ、
毎晩倒れるように帰宅し、命のバトンをつなぐのに必死でした。
三人の子どもを産んだ今の私であれば、
つわりがどれだけひどくても、ゲーゲー吐き続けながらでも、
祖母と医師に会いに行き、積極的に関わっていたと思います。
しかし、
あの時の私にはできませんでした。
何事も、タイミングというものがあるのに
自分とお腹のこと以外考えられず
医療機関がちゃんと見てくれているから大丈夫だと思っていました。
しかし結局、
予備力のない状態で胃瘻を造設された祖母は、
その後上向いてくることはなく、息を引き取りました。
最愛の祖母に、
私の初めての子供を見てもらいたかったのに。
ひ孫の顔を見てもらうことは叶わず、祖母は出産1か月前に亡くなりました。

私はこれまで
約3万人の患者さんの栄養管理に従事してきました。
3万人もみてきたのに、
たった1人、
無償の愛を注いでくれた
たった1人の最愛の祖母に、
十分なサポートをしてあげられませんでした。
なんで?
どうして?
何が栄養管理だ
何がチーム医療だ
どれだけの症例数をみてきたと思っているんだ
何のためにこの仕事を続けてきたんだ
あの時、
もっと早く知っていればできることはたくさんあったのに
専門家として、
関わる家族全員に、
適切な情報をより丁寧に説明できたはずなのに
何よりも医師に、
相談の場を設けてもらえるよう働きかけるべきでした。
自分の専門分野なのに。
最愛の祖母と、
苦しむ家族を支えることができませんでした。
もう、後悔の嵐です。

長寿大国ニッポンにおいて、
超高齢者に胃瘻を造設することはありますが、
あの時
適切に関わることができていれば、
おそらく胃瘻を造設することはなかったと思います。
そしてあなたにぜひお伝えしたいことは
「家族が元気なうちに、
最期をどのように過ごしたいのかを話し合っておくこと」です。
もしあなたが、
あなたの大切な人について
医師に
「どうしますか?」と問われたら、
きちんと家族の意見をまとめて
納得できる意思決定をすることができるでしょうか?

これはとても大事なことなのです。
元気な時だからこそ、時間をかけて話し合える話題です。
我が家の場合、
本来であれば、あの時、
残された家族が悲しんで見送るのではなく、
「大往生おめでとう!!」
と
おめでとう、と言えたはずなのです。
大往生ですもの。
家族全員で、
おめでとう!と言えたら良かった。
お葬式の時に泣くのではなく、
「おばあちゃん頑張ったよね~!」と、
見送る家族も笑顔にもなれたでしょう。
しかし結果として、そうはなれませんでした。
私としては、
後悔の念と、
祖母が入院していた医療機関に対する疑問もあいまって、
どのように向き合えばよいのか悩みました。
疑念と
怒りと
無念さと。

悩みに悩み、
そして行き着いたのは、
祖母の死から得た教訓を、
「医療現場に生かすことが、自分の役目だ」という気づきでした。
私がよく、家族が健康なうちに
「どのような最期を迎えたいのか話し合っておくといいよ」
とお薦めするのは、この経験からです。
そもそも、
医療機関によって
栄養管理に温度差があるのはおかしなことです。
この格差をなくしていかなければなりません。
それからというもの
同じことが起こらないよう、
粛々と患者さんの栄養管理に向き合いましたし、
医療従事者同士で学び合えるチーム医療にも一層力が入りました。

目の前の患者さんを
「自分の本当の家族」と思って接してきましたし、
チーム医療における自分の役割を全うしようと努めてきました。
そして
祖母の死から8年が経過した時、私のキャリアに転機が訪れました。
「介護離職」することになったのです。
義両親が病いに倒れ、介護のため、
夫のふるさとである愛媛県に転居することになったのです。
紆余曲折を経て、医療の現場を離れました。
そしてまた、
新たな悩みが生まれました。
私から病院管理栄養士の仕事がなくなったら
何ができるのか?
臨床現場における私の使命は十分に果たせたのか?
臨床の場を離れてもなお、私には責任があるのではないか?
育児と介護のケアに並行しても、
今ならまだ余力がある。
悩み、
迷い、
色々な人生の先輩に会いに行きました。
自分がすべきことを探し、
ようやく
その方向を見定めることができました。

これまでの22年は、
患者さんの栄養管理に邁進してきました。
これからは患者さんではなく、
将来患者となるリスクを抱える方を
医療機関の外から守ること。
これが私の役割であると考えるに至りました。
まだ医療機関にかかっていないが、健康不安を抱える人、
あるいはすでに健康リスクを指摘された人に対して、
適切な食のあり方を広めること・・・
これなら医療機関を離れた私にもできる。
そして
医療機関の外側で、
まず、私が貢献できることは
生活習慣病の退治であると考えています。
私一人では微力ですが、
本気で、
この病気を消してしまいたいと思っています。
生活習慣病は唯一、
自分である程度コントロールできる病気です。
なぜかというと、
生活習慣を握っているのは、他の誰でもないあなただからです。
医療機関でしか治療できない病気もありますが、
生活習慣病なら、自分でコントロールできる。
医療機関であっても治療できない病気がある一方で、
生活習慣病なら、ある程度自分でコントロールできるのです。
生活習慣病というのは、
やろうと思いさえすれば、
自分でコントロール良好な状態へ持っていくことができる、
ただ一つの病気です。

「病気になったら病院に行けばいい」
ではなく。
「検査結果が悪くても薬を飲めば何とかなる」
ではなく。
本来であれば自分の健康は自分で守る。
そのための健康リテラシーを持っておくべきですし、
それは自分だけでなく、
大切な家族を守ることにも直結します。

もし近い将来、
皆保険制度が消えてしまったとしたら??
あなたは自分自身と、
あなたの大切な人を守れると思いますか??
本当に守れる??
皆保険制度の日本ですが、
この制度があるが故に、
日本人の予防医療への関心は高いとはいえません。
健康リテラシーも十分にあると言えるのでしょうか。
どれだけあなたが
その道のスペシャリストだとしても、
どれだけあなたが
その人を大切に思っているとしても、
肝心な時に支えられないようでは、
後に残るのは後悔ばかりです。
そんな思いを、私はもう二度としたくありませんし、
あなたにもしてほしくないと思っています。

医療機関の外で働いたことがないので、
外に出た私に何ができるのか、
どのように取り組めばよいのか分からず、
しばらく立ち尽くしていました。
しかし、
自分に課せられた責任を
過小評価するのはやめることにしました。

私が発する情報によって、
あなたの身体がもっと健康になるかもしれませんし、
実は今、あなたが晒されているリスクを
あなたに伝えることができるかもしれません。
あなたの健康リテラシーが向上することによって、
あなたの大切な人を守ることにも繋がるかもしれません。
「今は忙しいから、もう少し区切りがついてからにしよう」
とか、
「これが終わったらやろう」
とか、
実は、そんな時間はないのかもしれません。

「これが一段落ついたら」
「これが終わればキリがつくから」
と考えている内に、
本当であれば守れたはずの、
あなたや
あなたの家族、
あなたの大切な人の
健康を損なってしまうかもしれません。
あの時は苦しくてできなかったけれど、
振り返れば
あのタイミングしかなかったのに、
と後悔し続けた過去の私のように。
あんな風にはもうなりたくないのです。
もしかしたら、私にもあなたにも、
先延ばしできる時間は、
実はあまりないのかもしれません。

だから私も、一歩前に踏み出すことにしました。
あなたとあなたの大切な人の健康を守るために、
全力で、
持てる限りの知識と経験をお届けすることにしました。
病院の外で働くことがなかったので、
右も左も分からずにいますが、
私の発する情報が、
あなたの健康を守り、
あなたの大切な人をも守ることに繋がりますように。
全ての経験を活かして取り組んでいきます。
職歴22年のうち20年間を、
東京都千代田区にある急性期総合病院で勤務。
ICU・内科・外科・緩和ケア病棟を含む全病棟、29の診療科の栄養管理に従事。
上司・同僚に恵まれ学会発表や論文・医学書・医学雑誌の執筆を多数経験。
日本病態栄養学会NST※臨床研修施設 として、
長年院外医療スタッフへの研修指導を担当。
介護のため、2025年に退職。
※NST:(Nutrition Support Team 栄養サポートチーム)
管理栄養士国家資格のほか、以下の認定資格を保有(2025年現在)。
- がん病態専門管理栄養士研修指導師
- 糖尿病療養指導士
- 病態栄養専門管理栄養士
- NST専門療法士
- 1981年 埼玉県与野市生まれ
- 1996年 タイバンコク日本人学校中学部卒業
- 1999年 大妻嵐山高等学校卒業
- 2003年 大妻女子大学卒業
- 2003年 委託給食会社に入職
- 2005年 東京逓信病院 栄養管理室に入職
- 2025年 介護のため同病院を退職